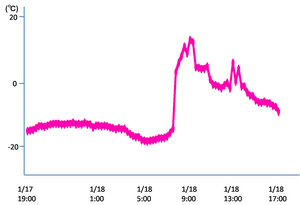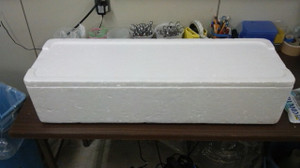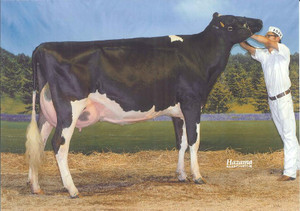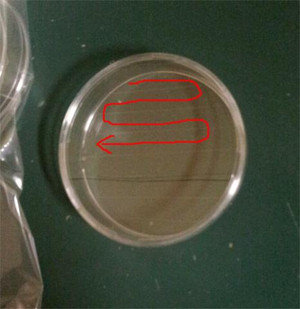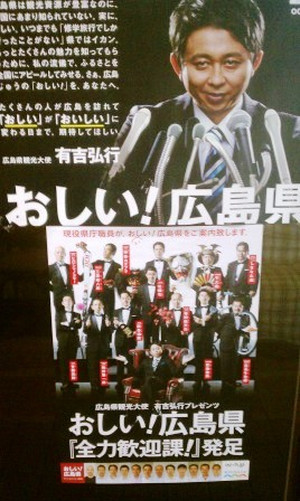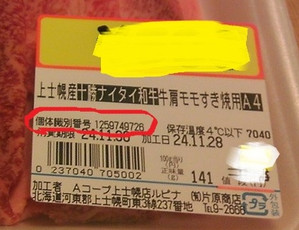国際胚移植学会 in ドイツ
現在ドイツのハノーファーで国際胚移植学会が開催されています。
このブログもドイツからの更新になります。
(写真のファイルサイズが大きいのでなかなかネットにアップできません![]() )
)
世界中から研究者や、獣医師が集まって、繁殖に関する最新情報を共有しております。
↓ 会場です。
↓ 研究ポスターの展示会場です。
学会では、上のようなポスター展示による研究発表と(今回は337題)、
口頭による発表があります(言語は英語です)。
今回はヨーロッパで開催ということで、ヨーロッパからの参加者が多かったように思います。
戸惑ったのはイタリア人が話す英語はイタリア語に聞こえ、
フランス人が話す英語はフランス語に聞こえたことですね![]()
英語で話しかければ、皆さんフレンドリーですので
非常に有意義な情報交換の場所となります。
来年はラスベガスで開催のようです。
ぜひ参加されてみてはいかがでしょうか?